「話についていけてない…。 - mino 10/24-01:16 No.597」 より
エフェクトの基本的な知識を身につけよう、という話です。
「ビギナーのための・・・」というリクエストですが、ビギナーに毛が生えただけの私に
どこまで出来るか疑問です。
とりあえず始めてみますが、怪しくなってきたらすぐ終わりますので、あしからず。
パート1 <エフェクト>
パート2 <リバーブ>(一部修正)
パート3 <コンプレッサー>
パート4 <コンプのパラメーター>
パート5 <マスタリング・コンプ>
<エフェクト>
「エフェクトの分類」
いきなり興味の沸かない話題かもしれませんが、結構重要な部分ですので、
頭に入れておいてください。
分類といっても、色んな分け方があると思いますが、ここでは・・・
① 原音そのものに変化を付けて出力するエフェクト
② 原音とエフェクト音をMIXして出力するエフェクト
この二つに分けて進めていきます。
① の代表的なものは、ディストーション(歪み系)やコンプレッサー(ダイナミクス系)です。
② は、リバーブ・ディレイ(空間系)などです。
② の場合、原音を “ドライ” 、エフェクト音を “ウェット” といいます。
このあたりがどうして重要かというと、例えば ② のタイプのエフェクトを使う場合、
AUXバスにエフェクトを配置して使うケースがあるからです。
AUXを使うことによって、ドライ音とウェット音とを独立してコントロールすることが
出来ます。
AUX送りにした場合の効果ですが、簡単な作例を聴いてみてください。
・元音
・リバーブ1 インサート・エフェクト
・リバーブ2 センド・エフェクト
(MP3 各50KB)
元音にかなり深めのリバーブをかけてみました。
トラックに直接リバーブをかけた場合(インサート・エフェクト)、ドライ音が引っ込んでしまい、
音の輪郭がボケてしまってます。
一方、AUX経由(センド・エフェクト)にすると、トラック側でドライ音を残したまま、
AUXへ送った音にリバーブがかかってますので、元音の輪郭がはっきり残っています。
もちろん、パラメータの設定は両者とも同じです。
初回にしては、やや高度(でもない?)な話でしたが、ちょっと工夫すれば
こういう効果が得られる、ということです。
次回(本編)では、リバーブの各パラメータの説明や、実際にAUXを使う方法なんかを
やります。
ご意見は、掲示板のこちらへ。
<Reverb> (SONAR標準の “FX Reverb” の各パラメーターや、実際の効果について)
「リバーブの効果」
リバーブに限らず、ディレイ・コーラスなど空間系エフェクトの一般的な使用目的として、
- 音に、厚み・深みを与える
- 臨場感を出す
- 他のパート同士を馴染ませる
1.2. に関しては、説明の必要はないと思います。
3.は例えば、MIDI音源の音と、生録のギター・ボーカルとをミックスする場合なんかに、
大変効果を発揮してくれることがあります。イコライザーなどと併用すると効果的です。
またリバーブは、音を後ろに下げるような場合にも使います。
例えば、ストリングスに適切なリバーブをかける事で、あたかも、
ステージの後方で鳴っているような効果を与えることが出来ます。
「パラメーター」

- ・ ROOM SIZE
- 音場の広さの違いによる響きかたをシミュレーションします。
残響音の長さの違いではありません。
リバーブによっては、「ROOM Type」という表記の場合もあり、
また RoomSize と RoomType の両パラメーターを併用する場合もあります。 - ・ DECAY TIME
- 残響音の長さです。
Reverb TIME という場合もあります。
上記2つのパラメーターは非常に密接な関係にあり、普通 “ROOM Size” を
大きめにする場合は、DECAY Time も長めにとり、“ROOM Size” が小さい場合は、
短めにするほうがいいと思います。
大き目の “ROOM Size” で “Time” が短いと、残響音が途中で途切れたように
なってしまい、不自然なリバーブになります。
- ・ HIGH f ROLL OFF
- 高音域をどれだけ残響音に含めるか(だと思います)。
- ・ HIGH f DECAY
- 高音域のDECAY(残響の長さ)です。
- ・ DENSITY
- “密度” ということですが、リバーブの “品質” という言い方もできます。
ギターなどの連続音ではわかりにくいんですが、ドラムのキックやスネアで
この値を上下してみると、はっきり違いがわかります。
最低にすると、プツプツと細かく途切れたような残響音になりますので、
特殊な効果をねらう時意外は、最大値でいいんじゃないでしょうか。 - ・ PRE DELEY
- ドライ音が鳴ってから、残響音が鳴り始めるまでの時差です。
例えば、キックの「ドン」という音の場合、最小の“0ms”では、
「ドわぁ~ん」という感じ。値を大きくすると、「ドン わぁ~ん」という感じ?
ドライ音とウェット音とを分離する効果がありますので、ボーカルやリードパートで
音をはっきり出したい時に効果的ですが、値を大きくしすぎると逆効果です。 - ・ MOTION RATE/DEPTH
- 残響音にピッチ変化をつけます。かなり特殊な効果になりますね。
- ・ LEVEL
- エフェクト通過後の出力レベルです。
- ・ MIX
- ドライ音とウェット音との比率を調整します。
0%は、ウェット=0 、ドライ=100 のことで、リバーブがかかってない状態です。
前回に話したAUXを使う場合は、この値を 100% に設定し、ウェットの量は、
AUXで調整するのが正解(だそうです)。
「実際の設定」
これは好みの部分もありますので、ごく簡単に 「自然なリバーブ」 を目標に
試してみました。
・ ドライ100%
- ・スモール・ルーム・リバーブ (↓各パラメーターの値)
- 0.47 / 1.00 /20.00 /9.86 / 1.00 / 12.00 / 0.20 / 0.00 / 1.00 / 0.28
- ・ ラージ・ルーム・リバーブ
- 0.85 / 3.10 / 3.03 / 9.86 / 1.00 / 65.00 / 0.20 / 0.00 / 1.00 / 0.14
ドライ音が引っ込んで、一見広い場所でのリバーブに聞こえますが、
ラージ・ルーム・リバーブは、MIXを少な目にしてますので、ドライ音が
はっきり聞こえます。
(スモール・ルームの方、あらためて聴くと、リバーブ強すぎたので、修正しました。
パラメーターの数値も、修正済みです。 MIX 0.43 → 0.28)
特別な意図がない限り、“かけ過ぎない” 方がいいと思います。
(作例は、どちらもちょっとかけ過ぎ)
言うまでもないことですが、問題は他のパートとミックスした状態で、どう聞こえるか
ですから、ミックス後に気に入らなければ、また元に戻って一からやり直してまたミックス、
またやり直し・・・根気が必要ですね。
ではまた。
<コンプレッサー>
(その前に) こういうご意見もあります
連動企画<揚げ足シリーズ> - HIROYA 10/28-15:15 No.677
私一人では心もとないんで、どんどん揚げ足とりをお待ちしてます。
(訂正)
リバーブのパラメーターで、「HIGH/ROLL OFF」 となってましたが、
「HIGH f ROLL OFF」(→ ハイ・フリケンシー・ロールオフ)の間違いでした。
リバーブの次は、普通 “ディレイ” とか、“コーラス・フランジャー” なんですが、
諸般の事情により、“コンプレッサー” を先にやります。
(試用期間中の “Mastering Comp” が使えるうちに、という事情です)
「コンプレッサーの効果」
- 1.録音時に、設定したレベルより大きな音を
カットする。(圧縮する) - これは “コンプレッサー” というより “リミッター” の役目ですが、
基本的には同じものです(ちょっと乱暴ですが)。
主な目的はもちろん、レベルオーバーを防ぐためですが、録音後の処理を
し易くする目的もあります。
- 2.録音済みの音の、レベルの大きい部分を抑える。
- こちらをメインに話を進めます。
私、コンプレッサーのことは、よくわかってない事に気づきました。
んなもんで、詳しい説明は<揚げ足シリーズ>にお願いして、
幾つかの実例と簡単な説明で、お茶を濁したいと思います。
「EX.1」 TimeWorks CompressorX による、スネアドラムの処理。
下図はドラムス・パートの波形です。
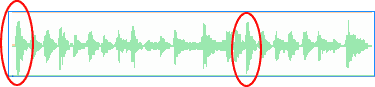
何箇所かに大きく飛び出した波形があり、このままで他のパートとミックスするには、
ドラムス・パートの音量をかなり絞らないと、レベルオーバーしてしまいます。
しかしそうすると、ドラムスの音量の小さい部分が更に小さくなってしまい、
結果、弱々しいドラムになってしまいます。
そこで、この波形の飛び出した部分だけを押さえ込んでしまおう、といわけです。
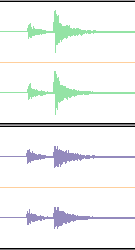 |
オリジナル (MP3 30KB) スネア・ドラムの弱打と強打です。 音量に大きな差があり、非常にミックスしにくい状態です。 CompressorX使用 (MP3 30KB) 弱打はそのまま、強打部分だけ小さくなってます。 波形がこれだけ圧縮されたにもかかわらず、 音は、それほど小さくなってないでしょう! (われながら、上出来!) |
このときの各設定は、下図の通りです。
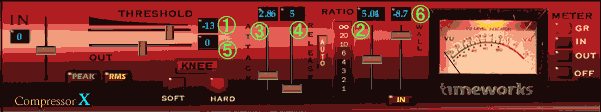
(各パラメーターの説明は、次回にします)
「パラメーター」
SONAR FX Compressor/Gate
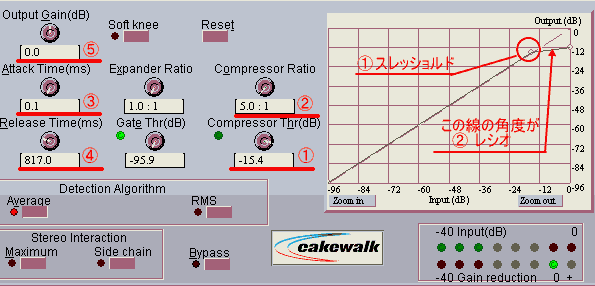
TW CompⅩと、SONAR FX COMP とでは、見た目は全く別物ですが、
基本的なパラメーターは同じです。
ただFX COMPの方は、Gateも兼ねてますのでそのためのパラメーターが余分にあります。
(今回 Gate は無視)
① Threshold(スレッショルド)
この値より大きなレベルの音を、圧縮します。
単位は “-dB” で、0 に近いほど圧縮が少なくなります。
② Ratio(レシオ)
元音に対して、どれくらい圧縮するかです。
単位は、“圧縮後 : 元音” の比率で表されます。
最大(∞)にすると、スレッショルド以上の音を完全に押さえ込んでしまいます。
③ Attack
フル・コンプレッションに到達するまでの時間。
最小値は “0.1ms” ですから、ほとんど瞬時にフル・コンプレッションに達します。
④ Release
フル・コンプレッションから、ゼロ・コンプレッションになるまでの、時間。
⑤ Out Gain
コンプレッサーからの出力時のレベルを調整します。
コンプ後はレベルが下がりますので、ここで適切にレベル調整してやります。
⑥ Wall
CompⅩ の方にだけあるパラメーターです。
PDFマニュアルによると、「OUT Gain の後にかかる」 となってます。
純粋に「リミッター」と考えていいんでしょうか???(フォロー希望)
今回のように、スネアの音を出来るだけ音質を変えずに抑えるには効果的でした。
書いてる私がよく分かってないぐらいですから、コンプを使ったことにない方には、
もっと分からないと思いますが、とにかく使ってみてください。
次回は、ミックス後にどういう違いが出てくるか、というあたりを攻めてみたいと思います。
色々と、ご意見・罵倒を頂いております。 連動企画コンプ<揚げ足シリーズ>
「マスタリング・コンプ」
ここまで、単一のパートでの使用例を紹介してきましたが、ミックス後に使うコンプも、
基本的には同じ考えでいいと思います。
ただ、SOANRのFX Comp や、CompⅩ は、マスタリング用途には向かないので、
(使いかたがヘタなのか)
ここでは、「AKAI Quad Comp(参照)」 と 「TW Mastering Compressor(参照)」を
使って、試してみます。
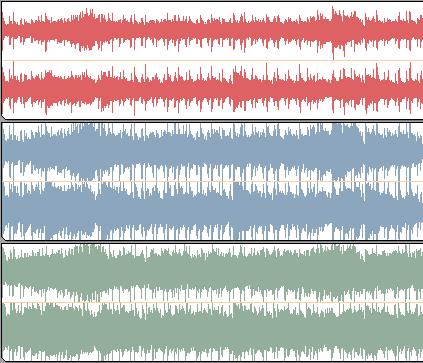 |
オリジナル (MP3 340KB) |
| TW Mastering Comp (MP3 340KB) |
|
| AKAI Quad Comp (MP3 340KB) |
オリジナルの波形では、キックと右寄りのライド・シンバルとが突出しており、
ノーマライズ後も全体的に細い波形になっています。
ミックス前の段階でこういう部分は、しっかり調整しておくべきなのは、
言うまでもありませんが、ミックス後にどれだけ修正できるのか、やってみました。
- TW Mastering Compressor
- ライド・シンバルが目立って、ちょっと聞きづらい感じもしますが、
元の素材が悪いので、仕方ありません。
これはイコライザーを併用することで、軽減できそうです。
低域が全く引っ込まないので、非常に力強い感じです。
スレッショルドを下げるだけで、自動的にこれだけの調整をしてくれるのは、
ありがたい! - AKAI Quad Comp
- こちらは、4つの帯域ごとに、手動で調整することになります。
ライド・シンバルが耳に付くので、高域をやや強めに押さえ、
低域も、弱くならない程度に多めにスレッシェルドを下げました。
TW より、落ち着いた感じになったと思います。
どちらもそれなりに、いいんじゃないかと思います。
コンプレッサーの使用に関しては、掲示板でもかなり突っ込んだところまで
語られていますので、詳しくはそちらをご覧いただくとして、とりあえず、
どんな効果があるのか、というところが分かって頂ければと思います。
また、掲示板でも指摘されましたが、“積極的に音作りに使う” という使用方法も
あります。
そのあたり、実際に使ってみて試されることをオススメします。
一応こんなところで、しめくくりたいのですが・・・。